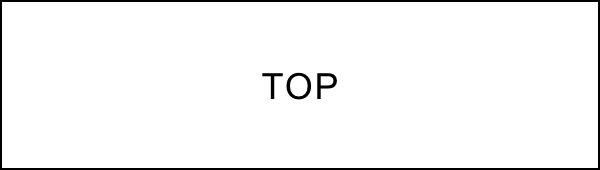石の一覧
岡部町 雑木の庭|建物とアプローチを緑で包む
2023.06.14|アプローチ石雑木雑木の庭高低差をデザイン
掛川市 外構・造園|雑木に囲まれた階段のアプローチ
2021.10.18|アプローチ浮き階段石雑木雑木の庭高低差をデザイン
浜松市東区 トキノハウス モデルハウス|雑木の庭
2021.08.11|ウッドデッキウッドフェンスオープンタイプ石雑木雑木の庭高低差をデザイン
掛川市 雑木の庭|軽やかさを感じる石階段
2021.07.19|アプローチ浮き階段石雑木の庭高低差をデザイン
豊橋市 雑木の庭|風が心地よい石張りのテラス
外構計画をする上で大切にしていること 〜SN Design Architectsさんの施工をさせていただいて〜
2021.05.23|アプローチオープンタイプ深岩石石石貼り雑木の庭駐車場
新城市 外構・雑木の庭|御影石のテラスが主役の庭
2020.12.07|オープンタイプ石雑木の庭高低差をデザイン
静岡市 外構・雑木の庭|アプローチから中庭を緑でつなぐ
静岡市 外構・雑木の庭|ほどよく視界をさえぎる、心地よい植栽
浜松市北区 外構|御影石のアプローチがある庭
2020.12.07|アプローチオープンタイプ石雑木の庭高低差をデザイン
島田市 外構・雑木の庭|印象的な古民家を引き立てる植栽
2020.12.04|アプローチオープンタイプ石雑木雑木の庭