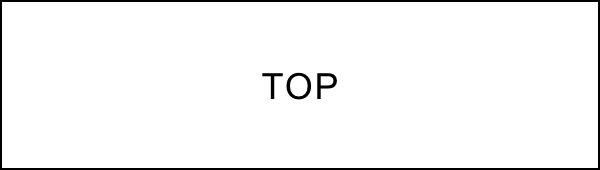駐車場の一覧
掛川市 外構|建物と調和したカーポート
2021.10.11|アプローチオープンタイプカーポート雑木雑木の庭駐車場
掛川市 雑木の庭|起伏をたのしむウッドデッキのある庭
2021.06.15|ウッドデッキ水脈水脈改善雑木雑木の庭駐車場高低差をデザイン
外構計画をする上で大切にしていること 〜SN Design Architectsさんの施工をさせていただいて〜
2021.05.23|アプローチオープンタイプ深岩石石石貼り雑木の庭駐車場
静岡市 外構・雑木の庭|水辺の上のアプローチ
袋井市外構・雑木の庭|角地を生かす植栽
2020.07.21|ウッドフェンスオープンタイプ大谷石雑木の庭駐車場
掛川市外構・雑木の庭|建物のファサードと呼応するウッドフェンス
2020.07.21|ウッドフェンスオープンタイプ雑木の庭駐車場
三協アルミ ワンダーエクステリアデザインコンテスト2019 表彰式
2020.02.08|オープンタイプカーポートコンテスト授賞浮き階段雑木駐車場
三協アルミ「エクステリアデザインコンテスト2017」 受賞式
静岡市外構エクステリア|ガレージ
2014.03.22|アプローチウッドフェンスガレージクローズタイプパーゴラ駐車場